|
|
|
|
| 目籠:中央市場で重さを量るのに使用。昭和40年から50年くらいまで。※プラスチック製がでるまではコレを使っていました。 |
| |
|
|
|

|
|
|
めど:
漁船の船底のイケスに水を通す部分に使用・昭和40年くらいまで。
※プラスチックがでるまで。時間があるときに作りだめしていた。 |
杓子:
食品工場の調理場からラーメン屋さんまでお湯を切るときに使用・昭和30年くらいまで。
※オーダーメイドで作成。大小いろんなサイズがある。 |
| |
|
|
|
|
|
篩:
左官職から和菓子屋まで、粉を篩うとき使用。
※網目のサイズが色々ある。3ミリから6ミリくらいまで。ヒノキ製の側に貼り付けていました。 |
|
|
|
|
樋受け:
ビルの屋上のパイプの上に被せて使用 |
七輪用網:
※七輪の上にのせて使用します。 |
|
|
|
|
裏ごし:料亭など。馬の尻尾の毛で編んだもの。
※毛をピンと張りながら編んでいく。社長が手で抑えてオヤジさんが張っていました。 |
|
|
|
|
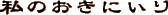
昭和40年くらいに、社長のオヤジさんがお孫さんのためにこしらえ、鳥かごのような大きさの虫かご。蛍も飼えます。ステンレス製なので丈夫。 |
|